私たち家族が諫早市馬渡町に住んでいたのは、
東大川の対岸にある「明倫館」に引越しをする前年の1981年まででした。
だから、今から34年以上も前の話です。
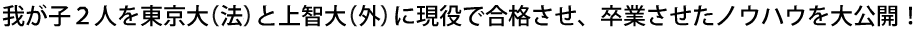

私たち家族が諫早市馬渡町に住んでいたのは、
東大川の対岸にある「明倫館」に引越しをする前年の1981年まででした。
だから、今から34年以上も前の話です。
日本には、かつてないほど外国人観光客が押し寄せています。
しかし、「少子高齢化」は待った無しで近づいているため、
国は「出入国管理の基本計画」に
経済成長に貢献できる外国人人材の受け入れを
大幅に増やす方針を打ち出しました。
具体的には、日本に滞在する在留資格の追加を検討しているようで、
「介護」や「技術管理職」を想定しているようです。
しかし、これから高校や大学を卒業する生徒や学生を
締め出すことに繋がらないかと心配しています。
私は、前にも何かの機会に述べましたが、
少子高齢化社会が出現することは、私たち「ベビーブーマー世代」が
第二次大戦後に生まれた時から分かっていたのです。
その後の「人口動態調査」、所謂「人口ピラミッド」から見ると
一目瞭然なのです!
しかし、政治家たちの「集票思惑」や
「官僚たちの自己保身システム」に阻まれて
国民的争点になってきませんでした。
それが、ひいては知恵と力のない若者や国民に
「出入国管理法」という法律でその場凌ぎをしょうとしています‼️
矛先は、海外まで向かいつつあると思います。
それが、次の記事です!
これも、一見すると日本が育んできた「日本式教育」のノウハウを
伝授する「美談」のように思えますが、
これも「少子高齢化」の影響で余剰となる人材や教材などを
「国際貢献」と言う美名の下に途上国に押し売りしているだけのことです。
「ODA」「JICA」だけが日本の武器ではないようです。
官僚たちの悪知恵は、
日本の「少子高齢化」を背景に
これからも益々巧妙化、複雑化、高度化していきそうです⁉️
真っ赤な花が特徴で、
しかも他の花のように葉っぱがありません。
花が散った後に葉が芽生えるという
他の花とは逆転していますが、
秋空の青に良く映える花ですので
私は結構気に入っています。
しかも、長崎では「赤い花なら曼珠沙華、オランダ屋敷に雨が降る〜」というフレーズで
坂の町長崎によく似合うと思いませんか❓
私が何時もウォーキングコースにしている道でも
良く見かけます。
ところで、どうして「曼珠沙華」というかというと
サンスクリット語から来ているそうですが、
「天界に咲く花」という意味で、
本来は「おめでたいことが起こる兆しに赤い花が天から降ってくる」
という仏教の経典から来ているそうです。
従って、「毒花」「痺れ花」「死人花」「地獄花」「幽霊花」などの名称は
その成分から来たり、咲く時期に由来したり、
植えられている場所から連想しているだけのようです。
しかし、本来は「おめでたい花」であることを理解しておきたいものです。
私が今一番注目しているのは
「シェアリング エコノミー」です。
最初に私が目にしたシェアースタイルは、
カナダのバンクーバーに行ったときに町の至る所で乗り捨てられた
ベンツのスモールカー「スマート」の電気自動車でした。
それから、「Airbnb」や「Uber」など目白押しとなってきました。
そういう「シェア」文化の背景には何があるのでしょうか?
新聞記事でも、最近時々話題になるようになってきました。
私は、その背景には
先進諸国に共通して現れている「少子高齢化」の現象が
あると考えています。
日本では今でも過剰なのに、これでもか、これでもかと言った具合に
作られられ続けてきています。
所謂、「スクラップアンドビル」というやつです。
しかし、空き家の例を持ち出すまでもなく、
余り過ぎているのです。
これから、益々その傾向は加速するでしょう。
そうすると余っているものを活用して
新しいものは作らないようにしないと経済が回らなくなる
飽和点が必ず来るでしょう。
そういうことの先取り現象が「シェアリング エコノミー」だと思うのです。
先日、三谷幸喜の「ありふれた生活768」を読んでいて
ふと論調が何か変だなと思って
よくよく読み返してみたら「だ・である調」と「です・ます調」を
混用していたのである。
それが、会話体の中で意図的に用いられていれば別なのだが、
地の文に混用されていたので変だと思ったのである。
話題が、山本耕史と堀北真希の結婚に関することであり、
三谷は、山本とは付き合いが深く、
また堀北ともテレビ対談をしたことがあるので、気を遣ったつもりであろう。
しかし、基本的には「だ・である」調と「です・ます」調の混用は
ご法度である。
三谷幸喜のように数多くの舞台や映画のシナリオを書いたりする人でも
間違うのだろうかと思った次第である。
「何か意図があって混用したのだろうか?」一度合って、聞いてみたいものである。